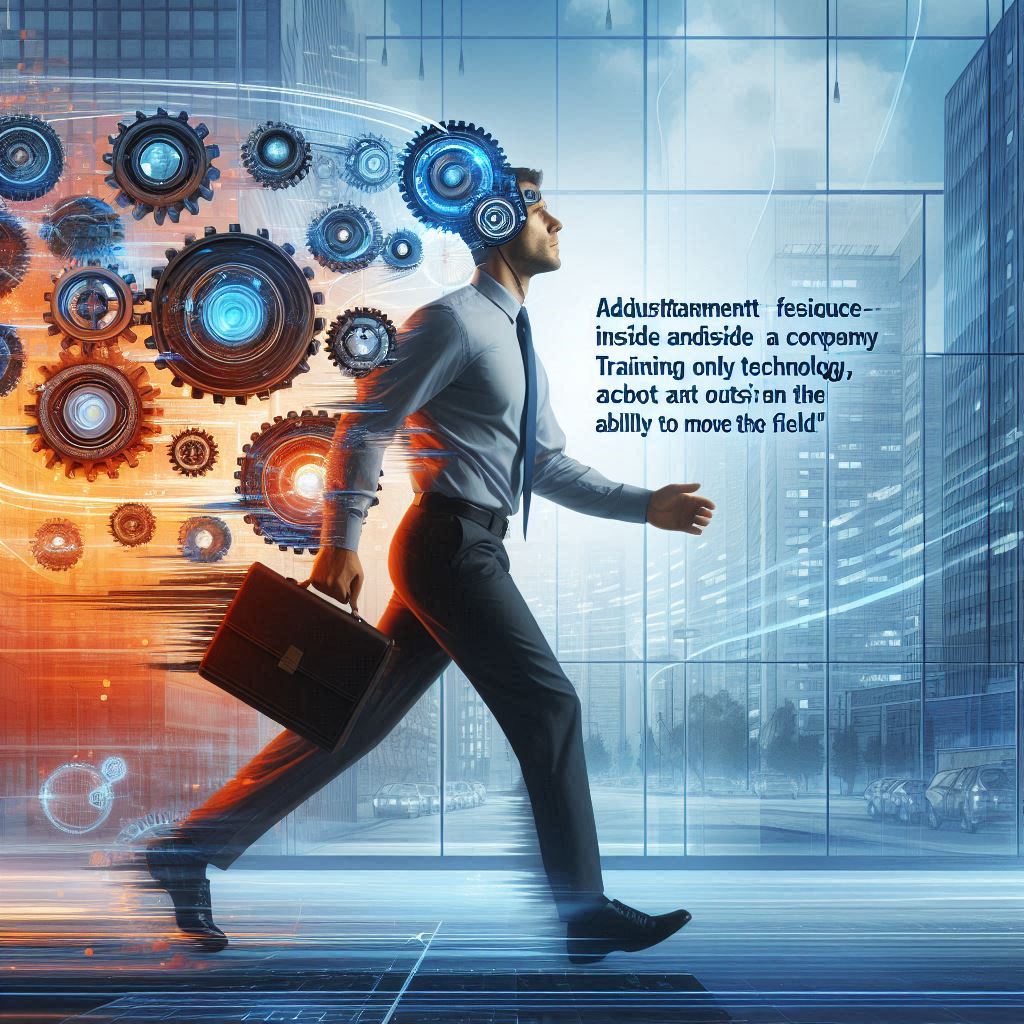
はじめに:SEの仕事は「調整業務」で8割決まる?
ソリューションエンジニア(SE)やプリセールスは、技術力だけで評価されるわけではありません。
プロジェクトが前に進むか、社内外の関係者を巻き込めるかは、**「調整力」や「ファシリテーション力」**に大きく依存します。
でも現実は…
-
「またアジェンダがふわっとしたまま会議に…」
-
「営業と技術、顧客の三者間ですれ違いが続出」
-
「関係者が多くて、落としどころが見えない」
このような“調整疲れ”に日々悩まされていませんか?
本記事では、社内外の利害調整を円滑に進めるSEのためのファシリテーション術を、実践例とともに紹介します。
【1】なぜSEの調整は疲れるのか?3つの構造的要因
◆ 1. 顧客・営業・技術それぞれが「前提知識」が異なる
→ 同じ話でも受け取り方・言葉の定義がズレてしまう。
◆ 2. 会議が「目的ベース」ではなく「報告ベース」で進む
→ 話して終わり、決まらない、時間だけが過ぎる。
◆ 3. 自分が“潤滑油”になりすぎてしまう
→ 誰の視点でも話せるがゆえに、板挟みになりやすい。
【2】“疲れない”ファシリテーションの基本3原則
◆ 原則①:会議は「情報共有」より「意思決定」に絞る
→ 会議の目的を「何を決める場か」に明示するだけで、空中戦を防げる。
例)冒頭でこう言うと効果的:
「本日のゴールは、〇〇案について方向性を決めることです。」
◆ 原則②:関係者の“関心ごと”を言語化しておく
→ それぞれが気にしている「見えない前提」を先回りで拾う。
例)技術視点:「パフォーマンスに影響が出ないか?」
例)営業視点:「顧客提案にこの機能が含まれているか?」
例)顧客視点:「自社運用時の影響は?」
◆ 原則③:議事進行より「議論の交通整理」に集中する
→ 議論のフレームを用意することで、話を“比べられる状態”にする。
例)選択肢を整理して提示:
「この件は、A案(スピード重視)とB案(安定重視)の2つの軸で整理できます」
表:「SEが使えるファシリテーションテンプレート」
| シーン | 推奨フレーズ例 | 目的 |
|---|---|---|
| 会議冒頭 | 「本日のゴールは〇〇を決めることです」 | 目的と到達点の明示 |
| 意見が散らばった時 | 「いま出た意見を〇〇・△△・□□の3つに分類すると…」 | 話を整理し、収束させる |
| 方向性を示す | 「今はA案を前提に話を進めてよさそうでしょうか?」 | 議論の前提を揃える |
| 合意形成前 | 「各立場から見て、懸念点はほかにありますか?」 | 抜け漏れを防ぐ |
【3】現場で見た、「調整疲れ」からの脱却事例
◆ ケース:要件が決まらない週次ミーティング
あるSEは、要件定義が毎回ずれ込み、PM・営業・顧客が不満を募らせていました。
実施したこと:
-
会議の冒頭に「本日決めたいこと」を提示
-
フレームワークで選択肢を整理し、比較しやすく
-
クロージングで次回までの宿題と担当を明示
その結果、**「要件定義が1/3の時間で終わった」**。
まとめ:SEにこそ、ファシリテーションは「技術」だ
-
調整力は、経験とセンスだけでなく**“技術”として学べる**
-
話す前に“場の構造”を作ることで、感情的摩耗を避けられる
-
小さな習慣(目的提示・選択肢整理・視点の補足)からでも、成果は出る

